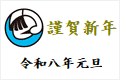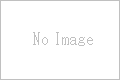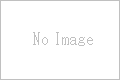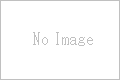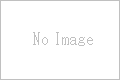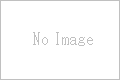明けましておめでとうございます。
本年も『悠但訪』をよろしくお願い申し上げます。
長かった酷暑の夏が終わったと思ったら、すぐに寒い冬になりました。
年々、春と秋が短くなって、四季から二季になってくるようです。
但馬の山々には雪が積もって、山歩きに出かけ難い季節になりました。
元々体力が弱いのに加えて、年々体力が減ってきているのを痛感しますが、
無理をしないよう気を付けながら、今年も歩きに出かけようと思います。
|
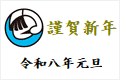
|
豊岡市竹野町の濱須井地区にある136m峰へ出かけました。
濱須井地区にある浜須井トンネルの西側の谷筋を回り込む所から作業道に入り、
途中で尾根に取り付いて山頂へ登り、南東にある八坂神社へ降るルートを周回しました。
尾根に並行する破線の道を歩く予定でしたが、入口を見つけられなかったので、尾根の先端付近から尾根の背を歩きました。
八坂神社へ降る尾根は急坂になっているので、樹木に掴まりながら降りました。
(散策メモ)
|

|
過日に、JavaScriptを使って二十四節気を表示する処理を先頭ページに入れましたが、
毎日が「冬至」になっていることに気が付きました。
テストした日が冬至だったので、この不具合には気が付きませんでした。
何故そうなるのか分からずに試行錯誤しましたが、
どうやらVar宣言をしていないローカル変数と同じ名前の変数を他の関数内で使うと、値が引き継がれるようなのです。
Var宣言をするように変更すると正しく処理できました。
|
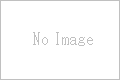
|
多可町加美区の奥荒田・寺内・的場の境にある525.0m峰(点名:的場山)へ出かけました。
県道8号にある新松か井の水公園を起終点とし、旧道を通って松か井の水を訪ね、
高坂峠の手前から作業道奥山3号線に入って森林基幹道笠形線に出て山頂へ登り、
森林基幹道笠形線に降りて新松か井の水公園へ戻るルートを周回しました。
作業道奥山3号線はかなり荒れています。
525.0m峰への登りと降りは急坂になっています。
(散策メモ)
|

|
本サイトの先頭ページに二十四節気の情報を表示するようにしました。
該当日になると、先頭ページの「プチ情報」の欄に、二十四節気の名前が表示されます。
以前作ったままにしていましたが、今回見直しを加えて表示するようにしました。
インターネットで計算式を見つけて作成しています。
2種類の計算式を見かけましたが、計算結果が微妙に異なります。
今回載せたのも少しズレるかも知れませんが、当面はこのまま表示するようにしておきます。
|
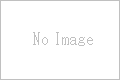
|
養父市・豊岡市・朝来市の境にある555.0m峰(点名:川見)へ出かけました。
豊岡市と養父市の境にある出石街道峠の南側から作業道を進み、
途中で支尾根に取り付いて市境尾根に出て山頂へ登り、北側を通る林道へ降るルートを周回しました。
尾根には明瞭な道はありませんが、「国土調査」や「兵公施界」などの境界杭が点々と続いています。
アセビなどが少し茂る所もありますが、薮漕ぎするほどではありません。
(散策メモ)
|

|
豊岡市の畑上地区にある168.7m峰(点名:新畑上)へ出かけました。
県道9号と県道11号の交差点付近を起終点として山頂へ至るルートを往復しました。
標識類は見かけませんが、「界」の赤プラ杭が続いています。
明瞭な道はなくて樹木も茂り気味ですが、行く手を阻むほどではありません。
木の根や岩などに掴まりながら登り降りする急坂もあります。
落ち葉に埋もれているのか、三角点の標石は見つけられませんでした。
(散策メモ)
|

|
豊岡市竹野町の竹野地区と森本地区の境にある295m峰へ出かけました。
竹野子ども体験村からジャジャ山公園へ続く遊歩道の途中から尾根に取り付いて、
272m峰を経て295m峰へ至るルートを往復しました。
295m峰へ続く尾根に明瞭な道はありませんが、少し樹木の密度が増す所もあるものの薮漕ぎするほどではありません。
295m峰には大きな展望岩があって、眺めが広がります。
(散策メモ)
|

|
田結峠へ出かけたついでに、過日に新調した万歩計を試してみました。
GPSログでの道程4.2kmほどを7000歩ほどで歩きました。
取扱説明書によると正確にカウントされない条件が幾つかあるようで、
どこまで正しく計数されたのかは分かりません。
GPSログの正確性も定かではありませんが、単純に割り算すると平均で一歩60cmになります。
山道を歩いたにしては長いような気もしますが、実際のところはどうなのでしょう。
|
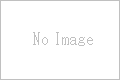
|
豊岡市の田結地区と京丹後市久美浜町の蒲井地区の境にある田結峠へ出かけました。
これまでにも訪ねていますが、今回は蒲井区公民館を起終点とし、
谷筋に続く古道を通って田結峠へ登り、北北東から東南東へ延びる尾根を通って八坂神社へ降るルートを周回しました。
古道は広めで明瞭ですが少し荒れ気味です。
田結峠から八坂神社へ降る尾根に明瞭な道はありませんが、薮漕ぎする所はありません。
(散策メモ)
|

|
拙作のルート図作成ツールをプチ改造して使い易くしました。
複数の文字列の外側を囲う場合、
これまでの矩形処理では各々の文字列の位置を確認しながら上下左右を調節する必要があって面倒でしたが、
これらを自動的に行う処理をグループ機能として追加しました。
囲う文字列群に大まかに掛かるようにグループの矩形を追加すると、それらの外側の矩形を自動的に計算して、
ぴったりと収まるような位置と大きさにする機能です。
|
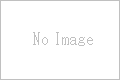
|
これまでの万歩計の動作が思わしくないので、新しいのを買いに出かけました。
多機能なのもありますが使い切れないので、歩数を計るだけの単機能なのを購入しました。
ポイントカードを出すとアプリへの移行を勧めてきます。
初回特典として付く500円のクーポンに釣られて、インストールすることにします。
手順が結構長いものの、店員に教えて貰いながら何とかインストール出来ました。
スマホを機種変更するとアプリがどうなるのか心配ではあります。
|

|
養父市にある杉ヶ沢高原へ出かけました。
11年前にも訪ねていますが、前回とは逆回りで天滝まで歩きました。
高原ではススキが茂る中に続く僅かな踏み跡を辿りながら進みます。
天滝までの急斜面には擬木の階段や鎖柵が設置されていますが、
土砂や落ち葉が厚く積もり崩れている所もあって滑り易く、かなり危なくなっています。
俵石へ向かう斜面は土砂や落ち葉が積もって道が分り難くなっています。
(散策メモ)
|

|
昨年の柿の収穫はゼロでしたが、今年は小さな木に鈴生りの大豊作でした。
何回かに分けて合わせて50個以上はお裾分けし、自分でも毎日のように食べてきました。
まだ多くの実が残っていますが、柔らかくなったり赤く熟して落ちたりするようになりました。
堅そうな実を選んで食べていますが、葉も落ちて終わりが近づいてきたようです。
来年は今年ほどは生らないでしょうが、お裾分け出来るほどには生って欲しいと願うのでした。
|

|
足の親指が少し快方に向かい始めたので、
確認も兼ねて、豊岡市竹野町と香美町香住区の境にある330m峰へ出かけました。
国道178号の旧道にある土生隧道の傍から尾根に取り付いて稜線に出て山頂へ向かい、
少し引き返した所から一つ東側の尾根を降るルートを半周回しました。
山頂は樹木に囲まれていますが、北西側に少し出ると山並みを見渡せます。
足を庇いながら慎重に歩いたこともあって、思いのほか時間がかかりました。
(散策メモ)
|

|
近場の神社からの帰り道で、朝露に濡れた苔に足を滑らせて転び、足の親指を痛めました。
登り時に気になっていて、『降り時には注意しないといけない』と思っていましたが、
実際に降る時になるとすっかり忘れていました。
転ばないようにと思って足を踏ん張った時に痛めたようです。
変色していて痛みもあるので、癒えるまでは山歩きに出かけられそうにありません。
|
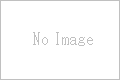
|
豊岡市竹野町桑野本と香美町香住区三川の境にある488.6m峰(点名:シシブシ)へ出かけました。
桑野本会館を起終点とし、集落の奥へ続く林道を詰めて稜線に出て山頂へ至るルートを往復しました。
稜線に続く林道の途中から尾根に取り付いて山頂へ向かいますが、山頂の手前で急傾斜の岩尾根になります。
途中まで登りましたが危険になってくるので、残念ながら山頂を目前にして撤退しました。
(散策メモ)
|

|
香美町香住区の安木地区と相谷地区の境にある269.5m峰(点名:安木)へ出かけました。
奥安木地区の奥へ続く農道を詰めた所を起終点として、峠道を登って稜線に出て山頂へ至るルートを往復しました。
峠道は途中までは明瞭ですが、峠の手前で不明瞭になります。
峠から山頂へ至る尾根は、植林地と雑木林を分ける僅かな起伏で続いています。
尾根や山頂の周囲には樹木が茂っていて、総じて眺めは広がりません。
(散策メモ)
|

|
神河町と多可町の境にある千ヶ峰(点名:千ヶ峯)へ出かけました。
今回は森林管理道水谷線の途中から水谷東ルートを登り、市原ルートに出て山頂へ至るルートを往復しました。
大師堂に出るまでの水谷東ルートは広い道ですが、石がゴロゴロして歩き難くなっています。
大師堂から市原ルートに出るまでは、作業道の敷設のために道が少し変更された所もあります。
山頂が近づくと段差の高い階段が続き、かなりバテました。
(散策メモ)
|

|
豊岡市但東町と京丹後市久美浜町の境にある高竜寺ヶ岳(点名:資母村)へ出かけました。
これまでにも何度か登っていますが、今回は北側を通る府道671号の峠付近から尾根に取り付いて山頂へ登るルートを往復しました。
尾根に明瞭な道はなく、アセビが茂ってプチ薮漕ぎの所や急坂の所もあって、想定していた以上に時間がかかりました。
少し雲は出ていましたが、山頂からは各方面に山並みを眺められました。
(散策メモ)
|

|
新温泉町にある上山高原へ出かけました。
以前にも訪ねていますが、今回は海上地区の海上公民館の傍から農道を経て稜線に出て、
左馬殿道と旧牛道を通って上山高原に向かいました。
農道の終点から稜線に出るまでは道が不明瞭の所もありますが、何とか稜線に出られました。
稜線は歩き易くなってはいますが、登り坂が続いてかなり汗を掻きました。
上山高原はススキが一面に穂を出して綺麗な眺めでした。
(散策メモ)
|

|
福知山市にある龍ヶ城(点名:辰ヶ城)へ出かけました。
今回は、2016年に登った時と同じく、北東側の小畑地区からのルートを往復しました。
山頂と尾根から少し山並みが見えますが、総じて眺めは広がりません。
前回よりも長い時間を要し、体力が落ちているのを実感します。
途中には急な岩尾根を登る所がありますが、
少し脇にもルートがあるようで、下山時には岩尾根を通りませんでした。
(散策メモ)
|

|
香美町村岡区の入江地区と長坂地区の境にある533.3m峰(点名:入山)へ出かけました。
県道135号の神坂バス停の傍から林道に入って空山中継局まで車で行き、そこから山頂まで歩いていきました。
山頂まで広い林道が続いていて、多少のアップダウンはあるものの、苦労することも無く山頂に立てます。
林道や山頂は樹木に囲まれていて、眺めの広がる所はありませんでした。
(散策メモ)
|

|
養父市八鹿町浅間と豊岡市出石町暮坂の境にある浅間峠へ出かけました。
県道2号の浅間トンネルの南西側出入口の傍にある駐車場を起終点とし、
地形図に実線で載っている道を通って浅間峠に出て、 北へ降って浅間トンネルを抜けて戻るルートを周回しました。
地形図に実線で載っている道は広めながら、アセビなどの薮漕ぎをする所や倒木が道を塞ぐ所もあって、
今では利用されていない道のようです。
(散策メモ)
|

|
香美町香住区の無南垣地区と久斗地区の境にある196m峰へ出かけました。
北側の作業道の終点から尾根に取り付いて山頂へ登り、
南へ伸びる尾根を進んで電波塔の保守路を降るルートを周回しました。
尾根に明瞭な道はなくプチ薮漕ぎする所もありますが、行く手を阻むほどではありません。
電波塔の保守路には金属網・横木・硬質プラスチック製の階段が途切れながら続いています。
(散策メモ)
|

|
香美町香住区の香住海岸がある半島を歩きに出かけました。
岡見公園の傍の駐車場を起終点として、東側の香住天文館を経て南へ降り、
長福寺と願行寺を訪ねてから、西側にある香住港城山灯台へ登り、
愛宕神社と八坂神社に立ち寄ってから駐車場に戻るルートを周回しました。
香住港城山灯台への道は広くて明瞭です。
灯台の手前には笹やシダ類などが茂っていますが、道の部分が刈り払われて歩き易くなっていました。
(散策メモ)
|

|
与謝野町と福知山市の境にある赤石ヶ岳(点名:赤石岳))へ出かけました。
2015年にも登っていますが、今回は北側の赤石林道から尾根に取り付いて山頂へ登り、
東側の尾根を峠まで降って加悦双峰公園へ出るルートを周回しました。
赤石林道から山頂までの尾根は、大小の岩が剥き出したり薮漕ぎをする所もあるタフなルートです。
途中でルートを誤ったようで、大きな岩が剥き出す岩尾根を苦労しながら登ることになりました。
(散策メモ)
|

|
朝来市生野町の真弓地区にある宮の谷渓谷へ出かけました。
2024年にも訪ねていますが、前回に分からなかった「参道中道」を歩くのが目的です。
最初の石灯籠が並んだ所に道の入口がありました。
塩ビ被覆のロープが見られる所もあります。
宮ノ瀧不動尊へ渡る小橋の手前にある標識が立つ所まで続いていました。
戻りは通常の行者道を歩きましたが、前日の雨で岩が濡れていて滑り易く、歩くのにとても苦労しました。
[散策メモ]
|

|
豊岡市の下宮地区にある204m峰へ出かけました。
西側にある金剛寺から主尾根に出て204m峰へ登り、
少し引き返して、195m峰と161m峰を経て「金剛の道」を降るルートを周回しました。
登り始めはプチ薮漕ぎする所もありますが、その先は比較的歩き易い尾根になります。
標識類は見かけませんが、所々にテープが巻かれていて、歩く人もいるようです。
山頂は樹木に囲まれていますが、尾根の所々からは山並みを眺められます。
(散策メモ)
|

|
香美町香住区の今子浦にある大引の鼻へ出かけました。
岬には大引の鼻展望台があって、近くにカエル島・千畳敷・但馬赤壁などの景勝地があります。
今回は今子浦の駐車場を起終点として、千畳敷やカエル島を訪ねてから大引の鼻展望台へ向かい、
但馬赤壁の尾根を少し歩いてから舗装路に降るルートを巡りました。
尾根の西側は断崖になっているので、少し東側を慎重に歩きました。
(散策メモ)
|

|
|