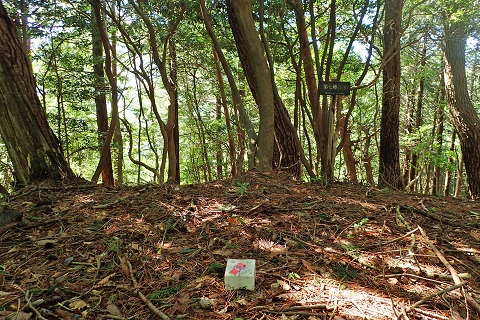|
【スライド1】
朝来市生野町から国道429号を北東へ進んでいきます。銀山湖の北側を進んで黒川温泉方面へ向かっていきます。平家板橋バス停を過ぎていくと、市川に架かる新平家板橋を渡った先に分岐があります。
|

|
【スライド2】
角には道標や標識などが幾つか立っています。「長野」の文字は見かけませんが、右側の道を進んでいきます。
|

|
【スライド3】
高路バス停を過ぎて、梅ヶ畑地区への道を右へ分けていきます。
|

|
【スライド4】
途切れながら続く植林地を抜けていくと、長野地区の集落のある開けた所に出ます。
|

|
【スライド5】
左へ分かれていく道を見送っていくと、路肩が少し広がった駐車スペースがあります。
|

|
【スライド6】
車で来た道を少し引き返していくと、来る時に見送った分岐があります。右の道へ入って谷筋の手前まで来ると未舗装路になります。
|

|
【スライド7】
谷筋を進み始めると分岐があります。標識類は見かけませんが、右の道は見送って正面の道を進んでいきます。
|

|
【スライド8】
よく整備されて路面も荒れておらず、小型車なら走れそうな道を軽く登っていくと、右側に浅い谷筋を幾つか見かけます。
|

|
【スライド9】
開けた所に出ると、道が分岐しています。標識類は見かけず、どちらへ行けば良いのかしばらく愚考しました。
|

|
【スライド10】
右の尾根が三国岳へ向かうルートのように思えるので、谷筋を挟むことになる正面の道は見送って、右の道を進んでいきます。
|

|
【スライド11】
少し降り坂になってきた道を進んでいくと、右の尾根が次第に低くなってきます。
|

|
【スライド12】
左への曲がり角まで来て、尾根との高低差が僅かになると、戻るようにして尾根へ登る踏み跡があります。
|

|
【スライド13】
尾根の上を見ると「姫路工業大学ワンダーフォーゲル部OB会」の設置した標識が立っていて、右の尾根を指しています。今回はここから尾根の背に出て三国岳へ登っていきます。
|

|
【スライド14】
植林地になった尾根の背を登っていきます。伐採木が散乱気味ですが、それほど歩き難くはありません。
|

|
【スライド15】
この尾根は朝来市と丹波市の市境になっているためか、「国土調査」の白頭短杭が点々と設置されています。
|

|
【スライド16】
尾根を真っ直ぐ登っていくと、尖った岩が頭を出す標高640mほどの高みに着きます。
|

|
【スライド17】
「第一峰(1/8)」の標識が立っています。
|

|
【スライド18】
樹間から僅かに山が見えますが、目指す三国岳でしょうか。
|

|
【スライド19】
少し左へ曲がって降り始める所に「地籍図根三角点」と刻まれた石標があります。
|

|
【スライド20】
植林地と雑木林を分ける尾根の背を降っていきます。
|

|
【スライド21】
鞍部に着いて、その先へ登り返していきます。
|

|
【スライド22】
尾根の樹木には黄テープが取り付けられています。細い雑木に取り付けられたテープも見かけるし山頂まで続いているので、登山道を示す目印のようです。
|

|
【スライド23】
標高630mほどの高みに着きます。
|

|
【スライド24】
「第二峰(2/8)」の標識が立っていて、手前には「8189B国土調査」の白頭短杭があります。
|

|
【スライド25】
少し左へ曲がって降っていきます。緩やかになった尾根を進んでいくと、左から登ってくる尾根が見えてきます。
|

|
【スライド26】
左から登ってくる尾根と合流する高みへ向かって登っていきます。
|

|
【スライド27】
傾斜が緩やかになって少し左へ曲がっていくと、標高650mほどの小峰に着きます。
|

|
【スライド28】
樹木の袂には矢印だけの標識があります。ここが「第三峰」かと思いましたが違うようです。地形図によると、ここを「第二峰」とする方が分かり易いように思えます。
|

|
【スライド29】
高みを過ぎて、植林地の尾根を軽く降っていきます。
|

|
【スライド30】
少し狭くなった鞍部を進んでいきます。
|

|
【スライド31】
尾根を登り返すようになると、左の樹間から僅かに山並みが見えます。
|

|
【スライド32】
雑木林に変わった尾根を登っていくと、標高650mほどの東西に延びる緩やかな高みに着きます。
|

|
【スライド33】
「第三峰(3/8)」の標識が立っていて、傍には「8304B国土調査」の白頭短杭があります。
|

|
【スライド34】
第三峰で尾根が二手に分岐していますが、東へ延びる尾根を進んでいきます。
|

|
【スライド35】
緩やかな尾根を進んでいくと、僅かな登り坂になります。
|

|
【スライド36】
「8311B国土調査」の白頭短杭のある高みに着いて、少し右へ曲がって降っていきます。
|

|
【スライド37】
傾斜が増してきた尾根を降っていきます。
|

|
【スライド38】
鞍部に着いて、その先へ登り返していきます。
|

|
【スライド39】
標高640mほどの高みに着きます。
|

|
【スライド40】
「第四峰(4/8)」の標識が枯れた大木に寄り掛かっています。
|

|
【スライド41】
第四峰でも尾根が二手に分岐していますが、左の尾根を進んでいきます。
|

|
【スライド42】
松の木が生える尾根を降っていくと、雑木林の鞍部に着きます。
|

|
【スライド43】
次第に登り坂になってくる尾根を進んでいきます。上の方に見えてくる高みへ向かって登っていきます。
|

|
【スライド44】
植林地になった緩やかな高みに着きます。標高640mほどの緩やかな高みの北東端のようです。
|

|
【スライド45】
「第五峰(5/8)」の標識と「8325B国土調査」の白頭短杭があります。ここでも尾根が二手に分岐しています。
|

|
【スライド46】
緩やかな右の尾根に引き込まれそうになります。
|

|
【スライド47】
黄テープが取り付けられた左の尾根を降っていきます。
|

|
【スライド48】
植林地と雑木林を分ける尾根を降っていくと鞍部に着きます。
|

|
【スライド49】
少し右へ曲がりながら登っていくと、左から尾根が近づいてきます。
|

|
【スライド50】
右前方には尾根の背が見えています。
|

|
【スライド51】
かなり急な斜面を登っていくと、左から来る尾根に登り着きます。
|

|
【スライド52】
脇には「8333B国土調査」の白頭短杭があります。
|

|
【スライド53】
右へ曲がって続く尾根を登っていきます。緩やかになったのも束の間で、すぐに登り坂になってきます。
|

|
【スライド54】
尾根の肩のような所に着くと緩やかになります。
|

|
【スライド55】
少し左へ曲がりながら進んでいくと、軽い登り坂になってきます。
|

|
【スライド56】
樹木が少し伐採されて明るくなった高みに着きます。
|

|
【スライド57】
四等三角点「弥六ガマ」があるので、地形図に載っている673.1m峰になるようです。
|

|
【スライド58】
三角点を過ぎて降り始める所に「第六峰(6/8)」の標識があります。
|

|
【スライド59】
雑木林の尾根を緩やかに降っていきます。
|

|
【スライド60】
軽い登り坂になってくると、尾根の肩に着きます。
|

|
【スライド61】
緩やかになった尾根を進んでいきます。
|

|
【スライド62】
再び登り坂になって尾根の肩に着くと、「8348B国土調査」の白頭短杭があります。
|

|
【スライド63】
右から登ってくる植林地の尾根を合わせて、植林地と雑木林を分ける尾根を進んでいきます。
|
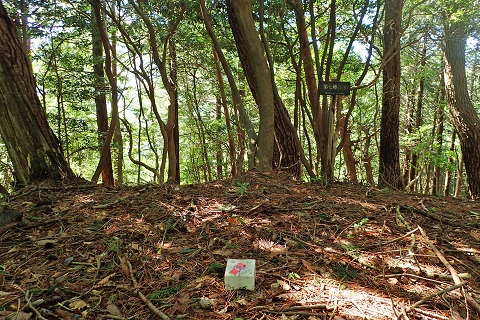
|
【スライド64】
登り坂になってきた尾根を進んでいくと、標高670mほどの高みに着きます。
|

|
【スライド65】
「第七峰(7/8)」の標識が立っていて、手前には「8351B国土調査」の白頭短杭があります。
|

|
【スライド66】
第七峰で尾根が三方に分岐していますが、左右の尾根は見送って、南方へ延びる真ん中の尾根を降っていきます。
|

|
【スライド67】
植林地と雑木林を分ける尾根を降っていきます。
|

|
【スライド68】
少し右へ曲がりながら、緩やかになった尾根を進んでいきます。
|

|
【スライド69】
少し降っていくと、緩やかな鞍部に着きます。
|

|
【スライド70】
左前方の樹間から山が見えますが、これから向かう三国岳でしょうか。
|

|
【スライド71】
次第に傾斜が増してくる植林地の尾根を登っていきます。かなりの傾斜があって、次第に脹ら脛が痛くなってきます。何度も立ち止まって、吹き上がってくる谷風に涼みながらゆっくり登っていきました。
|

|
【スライド72】
雑木林に変わると、少し傾斜が緩んできます。
|

|
【スライド73】
「8365B国土調査」の白頭短杭の所まで登ると緩やかになります。標高690mほどの尾根の肩になるようです。
|

|
【スライド74】
次第に登り坂になってくる尾根を進んでいくと、右から登ってくる尾根が合流する小峰に着きます。
|

|
【スライド75】
矢印だけの標識が指す左の尾根を進んでいきます。
|

|
【スライド76】
緩やかな尾根を少し右へ曲がりながら進んでいくと、正面が明るくなってきます。
|

|
【スライド77】
根元に丸い瘤のある樹木を過ぎていきます。
|

|
【スライド78】
アセビが茂る高みに着きます。地形図に載っている713m峰になるようです。ここで尾根が左右に分岐しています。
|

|
【スライド79】
「第八峰(8/8)」の標識が立っていて、傍には「8373B国土調査」の白頭短杭もあります。
|

|
【スライド80】
左に見える三国岳へ向かって、それほど背丈が高くないアセビを掻き分けていくと、すぐに歩き易い尾根になります。
|

|
【スライド81】
浅い鞍部に着いて登り返していきます。
|

|
【スライド82】
次第に登り傾斜が増してくるので、樹木などに掴まりながら登っていきます。
|

|
【スライド83】
呼吸を整えながら休み休み登っていくと、傾斜が緩んだ尾根の肩に着きます。標高730mほどの緩やかな尾根になるようです。手前には「8377B国土調査」の白頭短杭があります。
|

|
【スライド84】
緩やかになった尾根を進んでいきます。
|

|
【スライド85】
程なくして登り傾斜が増してきます。
|

|
【スライド86】
振り返ると、樹木に邪魔されながらも山並みが見えるようになります。
|

|
【スライド87】
少し左へ曲がりながら緩やかに登っていきます。何度も振り返って山並みを眺めながら登っていきます。
|

|
【スライド88】
標高750mほどの僅かな鞍部に着きます。
|

|
【スライド89】
鞍部を過ぎて、その先の尾根を登り返していきます。
|

|
【スライド90】
次第に登り傾斜が増してきてまた脹ら脛が痛くなってくるので、休み休み登っていきました。
|

|
【スライド91】
少し右へ曲がりながら、傾斜が緩んできた尾根を登っていきます。再び登り傾斜が増してきて、また脹ら脛が痛くなってきました。
|

|
【スライド92】
「8392B国土調査」の白頭短杭の所まで来ると、傾斜が緩んできます。標高800mほどの尾根になるようです。
|

|
【スライド93】
少し進んでいくと、また登り傾斜が増してきます。
|

|
【スライド94】
左から登ってくる尾根が次第に近づいてくるのを眺めながら登っていきます。
|

|
【スライド95】
緩やかな尾根に出て少し右へ曲がっていくと、山頂が見えてきます。
|

|
【スライド96】
今登って来た尾根を指す矢印だけの標識を過ぎていきます。
|

|
【スライド97】
樹木が伐採されて明るくなった山頂に着きます。
|

|
【スライド98】
「三国岳山頂855m」の白い標柱と、三等三角点「三国岳」があるので、地形図に載っている855.1m峰の三国岳になるようです。
|

|
【スライド99】
山頂の東側が開けていて、山並みを眺められます。
|

|
【スライド100】
三国岳からの眺め(1)です。
|

|
【スライド101】
三国岳からの眺め(2)です。
|

|
【スライド102】
三国岳からの眺め(3)です。
|

|
【スライド103】
三国岳からの眺め(4)です。
|

|
【スライド104】
三国岳からの眺め(5)です。
|

|
【スライド105】
三国峠へ向かって、南西に延びる尾根を降っていきます。
|

|
【スライド106】
植林地を緩やかに進んでいくと、手前の樹木に邪魔されながらも山並みが見えます。
|

|
【スライド107】
少し左へ曲がって降っていくと、「三国岳登山コース1合目」の標識が立っています。
|

|
【スライド108】
標識を過ぎると林道に降り立ちます。林道を右へ進んでいくと、すぐにヘアピン状に右へ曲がっていきます。その角が開けていて、山並みを見渡せます。
|

|
【スライド109】
林道からの眺め(1)です。
|

|
【スライド110】
林道からの眺め(2)です。
|

|
【スライド111】
林道からの眺め(3)です。
|

|
【スライド112】
林道からの眺め(4)です。
|

|
【スライド113】
曲がり角から正面の植林地へ続く山道に入っていきます。
|

|
【スライド114】
「三国岳登山コース」の標識を過ぎていきます。
|

|
【スライド115】
植林地に続く山道を降っていきます。登って来た尾根には明瞭は踏み跡はありませんが、こちらには「山道」という雰囲気の明瞭な踏み跡が続いています。
|

|
【スライド116】
傾斜が緩やかになって尾根が広がってきます。
|

|
【スライド117】
左側に「播磨おどり場」の標識が立っていて、「この辺一帯の平地です」となっています。
|

|
【スライド118】
少し先に「御手洗池跡」の標識があって左を指しています。その方角には僅かに窪んだ平坦地が見えるので、それが御手洗池跡のようです。
|

|
【スライド119】
標識を過ぎて降っていくと、右下すぐの所を林道が通っています。ちょいと脇へ出てみると山並みを見渡せました。
|

|
【スライド120】
使命を終えたように地面に横たわる獣避網に沿って降っていきます。
|

|
【スライド121】
正面が明るくなってくると、林道の曲がり角に出ます。先ほど分かれてきた林道のように思えますが、確かめた訳ではありません。
|

|
【スライド122】
曲がり角から正面の植林地へ続く山道に入っていきます。入口には白テープが巻かれています。
|

|
【スライド123】
緩やかな植林地に続く山道を降っていきます。急坂が結構あった登りルートに比べると、何とも快適な道であります。
|

|
【スライド124】
少し降り傾斜が増してくると「三国岳登山コース2合目」の標識があります。
|

|
【スライド125】
「三国岳登山コース」の標識を過ぎて植林地を淡々と降っていくと「三国岳登山コース3合目」の標識があります。
|

|
【スライド126】
少し傾斜が増した植林地を降っていきます。
|

|
【スライド127】
右側の樹間から、すぐ下に林道が見えてきます。
|

|
【スライド128】
傾斜が緩んできた植林地を進んでいくと、山道は左へ小さくクランク型に曲がっていきます。
|

|
【スライド129】
左へ曲がった所には「三国岳登山コース」の標識が立っています。左へ続く道もある分岐になっていますが、右へ曲がって降っていきます。
|

|
【スライド130】
クランク型に曲がる所を過ぎて降っていくと、鞍部になった三国峠に着きます。
|

|
【スライド131】
「ここは三国峠です 三国岳登山コース→ 4合目 あと900m」の標識が立っていて、袂には「千ヶ峰・三国岳縦走路」の標識と「表銀座コース案内図」があります。
|

|
【スライド132】
手前の樹木には「三国峠」の標識が取り付けられています。
|

|
【スライド133】
正面の尾根を登り返していくと千ヶ峰へ続いているようです。
|

|
【スライド134】
左へ戻るようにして降っていく山道もあります。
|

|
【スライド135】
「生野町へ下山コース」や「長野へ」の標識が指す右の踏み跡を降っていきます。
|

|
【スライド136】
これまでの山道とは違ってあまり明瞭ではない踏み跡を降っていくと、林道の曲がり角に降り立ちます。
|

|
【スライド137】
標識類は見かけませんが、右へ続く林道を進んでいきます。
|

|
【スライド138】
谷筋を回り込むようにして続く緩やかな林道を進んでいきます。
|

|
【スライド139】
少し先で植林地が現れると、再び谷筋を回り込んでいきます。
|

|
【スライド140】
ヘアピンカーブを右へ曲がっていきます。
|

|
【スライド141】
谷筋を回り込んでいきます。
|

|
【スライド142】
眺めが広がる尾根の先端まで来ると、林道が分岐しています。
|

|
【スライド143】
右の道は登り坂になっているので、降り気味の左の道を進んでいきます。
|

|
【スライド144】
左に広がる山並みを眺めながら、緩やかな降り基調の林道を進んでいきます。
|

|
【スライド145】
手前で分かれてきた林道を正面に眺めながら進んでいくと、僅かな谷筋を回り込んでいきます。
|

|
【スライド146】
広がる山並みを眺めながら、尾根の先端を曲がっていきます。
|

|
【スライド147】
谷筋に差し掛かると、小さなコンクリート橋を渡っていきます。この辺りからが、地形図に実線で載っている道になるようです。
|

|
【スライド148】
残土や砂利などがある道幅が少し広がった所を過ぎて、その先へ緩やかに降っていきます。
|

|
【スライド149】
緩やかな所が広がってくると、道なりに右へ曲がっていきます。
|

|
【スライド150】
谷筋を回り込んでいきます。
|

|
【スライド151】
車止めチェーンがありますが、この時には鎖は脇へ束ねて置かれていました。
|

|
【スライド152】
コンクリート舗装になった道を進んでいくと、右への曲がり角から道が分かれていく分岐があります。
|

|
【スライド153】
右へ登っていく道の先にはサーフボードが置かれていて、「個人の山林に付き進入禁ず」と書かれているので、左側の林道を降っていきます。
|

|
【スライド154】
一旦未舗装になって再びコンクリート舗装された林道を降っていくと植林地へ入っていきます。
|

|
【スライド155】
植林地を抜けると分岐があります。
|

|
【スライド156】
右へ分かれて登っていく道には車止めチェーンが張られていて、古タイヤが取り付けられていました。
|

|
【スライド157】
再び未舗装になった林道を緩やかに降っていきます。
|

|
【スライド158】
僅かな植林地を過ぎていくと、何軒かの建物が見えてきます。
|

|
【スライド159】
真っ直ぐ降っていくと、舗装路の曲がり角に降り立ちます。手前には「千ヶ峰・三国岳線森林基幹道開設事業工事現場」の立て札があって、今来た林道を指しています。今回降って来た林道は千ヶ峰・三国岳線というようです。
|

|
【スライド160】
右の樹木の傍には「災害に強い森づくり」の案内板が立っています。それに載っている「整備箇所位置図」には、三国岳の山頂の傍まで続く林道が描かれています。
|

|
【スライド161】
右へ続く舗装路を進んでいきます。
|

|
【スライド162】
塩ビ管が引かれた水場を過ぎていきます。
|

|
【スライド163】
長野地区の民家が見えてくると、左側を流れる長野川に架かる小橋を見送っていきます。
|

|
【スライド164】
長野川の心地良い水音を聞きながら進んでいきます。
|

|
【スライド165】
長野バス停があります。
|

|
【スライド166】
長野川に架かる小橋を見送っていきます。
|

|
【スライド167】
水が張られて田植えの準備が整った田んぼを眺めながら進んでいくと、長野川が少し離れていきます。
|

|
【スライド168】
車を止めておいた駐車スペースに着きます。
|
|